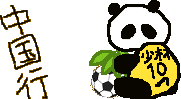 〜ナイロビの恐怖〜 際限なく続く林や平原が次第に人工の建造物に変わり、道幅は広く、並走する車の数も多くなる。頭上には、「NAIROBI」の表示。 ……きた〜っ。ついに来ちゃいましたよナイロビに……。ナイロビさん、お噂はかねがね聞いてましたよ。悪い噂ですけど(涙)。ヨハネスに次ぐ世紀末だって、角のタバコ屋の奥さんが言ってましたよ。 バスの窓からチラッと外を覗く。 ……な、なんだ? 道端に首から上だけを出して埋まっている人がいるぞ? 「あのお方の名をいってみろおーーっ!!」  「え〜〜っ!! ひええっ!!」 「ほら? どうしたあ〜〜っ!! 言えんのか〜っ!!」 「ひいい、し、知りませんっ!!」 別の男が埋まっている男の首にノコギリをあてがっている。 「なんだぁ? きさまもしらんのか!! やれ! さあノコを引くんだあ!!」 「あわわ〜〜っ!!」 銅像の名前を言えない男に、モヒカンの悪党が無理矢理ノコギリを……って今回もまた北斗の拳ネタに走っているわけだが、これにはれっきとした理由がある。アフリカ縦断組の男子の間では、南アフリカのヨハネスブルグは拳王の支配する都市、そしてナイロビはジャギがいる街と呼ばれ恐れられてているのだ。別にオレが考えたわけではなく、大体同年代の旅行者に会うと必ずこの話になるので、どうもこのネタはアフリカを渡り歩く男達の定説となっているようだ。ちなみに女子の間では、ナイロビはスケバン刑事が、ヨハネスは花のあすか組が……とかなんとかうまいことを書こうとしたのだが、残念ながらそっち方面は知識がないので断念する。 本来ならば先ほどのシーンの後に胸に7つの傷を持つ救世主が登場し、モヒカンの頭にノコギリをめり込ませ「あ……あら? ……バカ……おれじゃないるれ……ぱっびっぶっぺっ……ぽお(プシュ〜ッ←血)」と後世に残る名ゼリフを引き出すことになるわけだが、旅行記と一切関係ないためまたしばらく北斗ネタは自粛しようと思う。 バスが到着するのは、ガイドブックいわくいつどこで強盗や殺人が起こっても不思議ではないダウンタウンである。まだ昼間の3時ではあるが、恐怖感にさいなまれながら周りの景色を見ているとなんとなく殺人のひとつやふたつすぐにでも起こりそうな気がする。しかし「不思議ではない」と言うくらいだから、きっと殺人事件を目撃してもナイロビで買い物中の主婦達は、 「ええっと……お豆腐を3丁と、白菜と干しシイタケと……」 「ぎゃああ〜〜〜〜〜〜〜っ」←殺人 「あらあら。また殺人よ? 今日は2丁目のムワンザさんだわ。まあ、お気の毒に……。そうそう、あとスキヤキ用の牛肉を2キロと、エノキもちょうだいな」 と、太陽とシスコムーンがT&Cボンバーに改名と同レベルの死ぬほどどうでもいい出来事としてぞんざいに扱うであろう。 いよいよ終点にさしかかり、オレはそそくさと腕時計を外した。マレーシアで買った偽カルバンクラインではあるが、とりあえずアフリカの治安の悪い都市では腕時計や装飾品をつけていたら襲われるらしいので、襲われたくないオレは素直に時計をしまいこむ。時計が大事なのではない。年少時より25年来のつき合いである左腕が大事なのだ。実際にヨハネスで手首ごと腕時計を持っていかれた話を聞いたことがある身としては、当然の行為である。 ここでオレは提案したいが、ナイロビの治安回復の一案として、夜のダウンタウンを装飾品をしこたまつけて着飾った美川憲一や細木数子に歩かせ、強盗が1万人ほど集まって来たところで一斉検挙というのはどうだろうか?? それで大分犯罪者の数も減り、ナイロビに平和がやって来ると思うのだが……。 そんなくだらないことを考え、さらに「よし、この作戦のコードネームは美川のMをとってプロジェクトMと呼ぼう」などとくだらなさに具体性を持たせているうちに、遂にバスはダウンタウンの奥まった路地に停車。とりあえず真っ先にオレがしなければならないことは、荷物を受け取ったらすぐにタクシーを見つけ乗り込むことである。 幸いにして、バスの発着所だけあってタクシーの運転手が何人も客引きに来ている。 「ヘーイ、にいちゃん! タクシーか?」 「乗るけど、ちょっと待って。荷物が屋根に乗ってるから、受け取ってからね」 オレは、バスの屋根に上った荷物係が順番に乗客の荷物を下ろすのを、背後に数人のタクシー運転手の視線を感じながら待ちうける。来た。オレのバックパックだ。よいしょ……おや? なんかオレの荷物に同時に何本もの手が伸びていると思ったら、タクシーの運転手達の手である。 「ちょっと、自分で取れるから、大丈夫だって」 「いいから。オレがタクシーまで運んでやるよ!!」 とりあえず一刻も早くタクシーに乗り込むことが先決なので、この場は彼に任せようかなと思っていると、横から他の運転手がちょっかいを出し、なぜかドライバー同士の小競り合いが始まる。 「ヘイ! オレのタクシーの方がいいぞ!! こっちだ!!」 「なにを!!! オレが最初にこの日本人を見つけたんだろうが!!」 「関係あるかそんなの! その荷物をよこせよ! オレの車まで運ぶから!!」 「なんだとこら!! これはオレのもんだ!! 放すかよっ!!」 「よこせっ!! こっちに貸せよ!!」 「オレが運ぶって言ってるだろうがっ!! おまえはのろいんだから他の客を探せよ!!!」 「なんだこのヤロー!!!!」 ……。 無法地帯ですかここは。 一人の運転手がオレのバックパックに必死の形相で抱きつき、もう一人がこちらも必死でそれを剥がそうとしている。あんたら、どっちでもいいんだけど、その荷物はオレのだ。このまま放っておくと混乱が際限なく大きくなりそうだったので、オレは3人目の必死な男になり、自分のバックパックに飛びかかった。 「オリャー!! これはオレの荷物だ〜っ!! 誰にも持たせんっ!! 運ばせんっ!!! あんた、あんたが最初に声かけて来たんだよな。オレはあんたのタクシーに乗る。早く案内してくれっ!!」 「そうだろうそうだろう。さすが日本人は公正なジャッジメントだ」 「チッ……」 オレは自分でバックパックを抱え、少し怒った表情をしながら、しかしその実は他の運転手に殺されるんではないかと心臓の鼓動をレコーディング中の仲村トオルの音程くらい激しく乱しながら、縮み上がって最初のドライバーについてタクシーに乗り込んだ。 「よし、どこまで行くんだ?」 「えーと、この安宿まで・・・」 「そうか。わかった」 ゆっくりと運ちゃんは車を発進させる。ノロノロと走らせながら、なぜか彼は自分のすぐ横のドア、そして反対側、さらに今度はオレのいる後部座席のドアまで、全て手を伸ばしてロックがかかっているか念入りに確認をしている。 ……。 あの、怖いんですけど。 そんなに鍵を確認するってことは、過去に鍵が開いていて途中でドアを開けられ……引きずり出され……ダウンタウンの真ん中で……いつ強盗、殺人が起こっても全く不思議ではない…… ひええ〜っ。 とりあえずオレは、本来2m近くある背丈を思いっきり縮め、さらに外から見ても黒人に見えるように、心の中で松崎しげるの真似をしながらグッバイマイラブを歌った。ああ、これでなんとか黒人の仲間だと……思われるわけねー。 ダウンタウンを抜けるまでは意外に早く、アップタウンというかナイロビの中心部との境目であるモイアベニューに出ると、高層ビルなども目につき、やや街の喧騒は落ち着いて来たように見えた。 目指す安宿は古ぼけたビルの8階にあり、タクシーから降りるとオレはすぐに薄暗いエレベーターに乗り最上階へ向かった。乗っている間も途中の階で止まる度に、ドアが開くとナイフを持った強盗が待ち構えていて、無理矢理引っ張り出されて暴行を受け身ぐるみはがされるというマイナス方面の妄想がオレの頭を支配し、このエレベーターはオレにとっては富士急ハイランドのFUJIYAMAを遥かに超える絶叫マシーンであった。 最上階で降りてもまだ階段を登り、やっと宿の看板が見えて来たが入り口は頑丈な鉄格子で閉ざされている。宿のドアに鉄格子があるのは南アフリカはケープタウンと同じだが、ここのものはそれとは比にならない、レクター博士でも脱獄不可能と思われる重々しいものだ。 「す、すいませ〜ん。客なんですけど、中にいれて、いれてください〜(号泣)」 ギイッ……  ぬおっ!! マサイ族だっ!!!! なんとこの宿は、門番にマサイ族を使っているらしい。なかなか日本には無いシステムの宿だ。 「は、ハロー。あー、ココ、コンバントマレマスカ?」 「……」 言葉通じねー(涙) 何語? スワヒリ語? マサイ族語?? どれも喋れねー(号泣) 「……カモン」 彼は全く無表情のまま殺気立った眼光を放ちオレをジロジロと見つめ、やがて中に入るように首で合図すると、再び鉄格子に鍵をかけ、先立って奥へ進んで行った。……。なんか間違って盗賊団のアジトに来てしまったらしい。 といいつつ、中に入るとそこではちゃんとした盗賊団の宿が運営されていた。やや混んでいるようだったが、ここも一部屋にいくつもベッドを詰め込んだドミトリー形式のため、空いているベッドがあり無事チェックインできることに。ちなみに、ここには先客として2カ国ぶりに会う日本人がいた。 「あっ。どうもこんにちは」 「ああ、どうも」 「この度となりに越して来ました作者と申します……あの、これつまらないものですが……」 「いやいや、そんな気を遣っていただいて……」 「あの……ぶっちゃけ、この辺の治安ってどうなんですかね??」 「あはは……。まじでやばいですよ。半端じゃないです」 「ふーん。……あの、どんなふうに?」 「この街、そこら中に昼真っからシンナー吸って目が死んでるガキどもがいるんだけどね、」 「ほう」 「まあガキっていってもこのヘンの中学生くらいの年のやつはもう大人なみに凶暴なんだけど……つい2,3日前に、ここに泊まってた娘が夜3軒先の店に買い物に行ったら、宿を出た瞬間そいつらにボコボコにされて、身ぐるみはがされて瀕死の状態で帰って来たんだよ」 「……聞こえない。僕には何も聞こえない」 「まあ他にもいろいろあるけど……とにかく命が惜しかったら、日が落ちてきたら絶対に外に出ないことだね」 「はい。命が惜しいのでそのようにさせていただきます」 あははは…… 噂には聞いていたが、火の無いところに煙は立たぬとはよく言ったものだ。道すがら「なんでみんなこんなにナイロビを悪く言うんだろう?」と思っていたけど、本当に悪いからだったんだね。 とりあえず宿は確保できたため、夜は早い時間にベッドに入った。 一日緊張していたためか、すぐにウトウトしだす。開いている窓からは、このビルから道を一本隔てたダウンタウンの騒音が休み無く聞こえてくる。 zzzzzz…… パーン!!! パーン!!! うわ〜〜〜〜〜〜〜〜っ!!!!!!! ……。 銃声っすね……2発……。 ……。 聞こえない。何も聞こえない(号泣)。 今日の一冊は、完本 1976年のアントニオ猪木 (文春文庫)  |
TOP NEXT