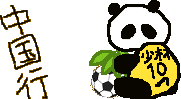 〜北上〜 「シゲキさん、コリオリの力の実験って見ました?」 「うん。あれはねー、インチキなんだよね。オレ自分のペットボトル使って実験してみたんだけど、全然理論どおりにならなかったから。所詮あんなしょぼい実験器具じゃあアホな旅行者をダマして小銭を稼ぐくらいしか使い道がないんだよ」 「ガーン!! 大造じいさんとガーン!!!」 「少人数にしかわからない驚きかただね……」 「うぬぬぬ……あのニセ教授め……オレをアホな旅行者にしやがって……」 「いや、別に作者くんがアホな旅行者って言ってるわけじゃ」 「いいんです! どうせ僕はヤングジャンプの『アイドルテレカ応募者全員サービス』の企画に申し込んで『すごい! 全員サービスなんて集英社はなんて太っ腹なんだ!!』と800円分の切手を同封したことも忘れて大喜びする人間ですから」 「アホだね……」 夕方になって偶然にも出会った世界一周中のシゲキさんと、オレは路肩のチャイ屋でお茶をしていた。最近世界一周中の旅人と会う機会が多いが、よく考えれば世界一周の途中でもなければこんな町で会うわけがない。日本からツアーでこの町に来ても、赤道で記念写真を撮ってコリオリの力でボられて1時間でツアー終了である。ついでだからとナイロビまで足を伸ばしてもいいが、強盗に遭ってもあくまで自己責任の問題で片付けられるのを覚悟しなければならない。 まあとにかくあの教授のコリオリ実験はイカサマだということが発覚した。おのれ〜。どうやら日本ではオレオレ詐欺ブームの真っ只中、ケニアではコリオリ詐欺が横行しているらしい。コリオリ詐欺の学校なんかもあったりして……。 ところで、オレはむき出しのコンクリートに囲まれたボロ部屋で一晩を過ごすわけだが、シゲキさんは違う宿だしここは個室なので夜は考え事をするくらいしかやることがない。考える内容は「自分がオリンピックでメダルを取るとしたらどの種目が一番かっこいいか」とか「プロレスの技名で一人古今東西」とか様々なのだが、この夜ずっと考えていたのは、「今この町の季節は夏なのか冬なのか」ということだ。 基本的に、日本が夏の時期にオーストラリアは冬であるというのはよく知られていることだと思う。これは大橋巨泉が夏になるとオーストラリアに住み出すことからもわかるだろう。北極と南極を貫く地軸が傾いていることにより、地球の公転とあいまって北半球と南半球は季節が全く逆になるのである。ちなみにこの地軸の傾いている角度が23.4度反対からだと66.6度という奇跡的に覚えやすい数値で、中学時代とても助かったことを思い出す。ありがとう地軸さん。ただし、あまりに覚えやすいため教師もそこはよくわかっており、中間試験などではこの23.4度という角度は最初から問題文の中に組み込まれているという悲しい結果になったりもする。 まあ中間試験はどうでもいいとして、がんばって話を元に戻すと、とにかくずばり北半球と南半球は正反対の季節なのである。 ……。 ちょっとまて。 ってことはシドニーオリンピックは夏季オリンピックなのに真冬に行われていたということか? あのオリンピックは2000年の冬季に行われた夏季オリンピックなのか?? わけがわからんぞ。 ええい、その話は帰国してから考えるとして、今悩むべきはここナニュキの町の季節である。北半球と南半球が逆であるならば、現在1月のこの町は真夏と真冬が同時に来ているということではないか。学校では夏休みと冬休みが同時、テレビでは恐怖心霊特集とホームアローンが同時に見れるということだ。 そして、とりあえずオレはこの不思議な町を紹介しようと証拠写真でも撮ろうと考えたのである。 ということで、翌朝オレはカメラマンとなってもらうべくシゲキさんの宿を訪問し、ドアをぶち破ってたたき起こした。一応「あの、赤道で僕の写真を撮って欲しいんですけど」と簡単に事情を説明すると、「てめーそんなことでわざわざ起こすんじゃねーよ」という憎しみの表情を一瞬浮かべたが、そこはさすが大人、最近生まれたいとこの子供を押し付けられ「作者おじちゃんに遊んでもらいなさ〜い」と言われても徹底的に無視するオレとは違い、「じゃあちょっと着替えるから待ってて」とにこやかに穏やかに引き受けてくれた。ちなみに親戚全員のオレを見る目は買ったばかりのipodのように限りなく白い。 赤道直下なのになぜかできうる限りの厚着をしたオレは、シゲキさんを無理矢理タクシーに押し込み赤道へ向かった。暑い(涙)。 タクシーの中で趣旨を説明しなんとか賛同を得たオレは、まず赤道の看板の下、北半球方面に立ちめちゃめちゃ寒そうな格好をした。土産物屋の黒人どもがオレ達を見つけてわらわらと寄ってくる。 「おい、おまえそんなカッコして、寒いのか??」 「ああ寒いさ。寒いからちょっとフレームアウトしてくれるか」 ヒマな店員達を無理矢理カメラのフレームから追い出し、真冬バージョンを撮影。そして南に2mほど移動すると、すかさず服を全て脱ぎ去り、ズボンも靴も履き変える。再びわらわらと寄ってくる黒人たち。 「お、おい、おまえどうしたんだ? 暑いのか??」 「そうだよ!! 暑いんだよっ!!!! ちょっとだけでいいからオレの周辺を空けてくれ!! ギブミースペース!!」 「よくわからんやつだな……」 こんなケニアの赤道直下の田舎町まで来て、町の住人に変人扱いされるオレ。しかし変人で本望である。というより変人のふりをしているわけであって、本当は行動は全て計算ずくの変人なのである。そして理解と協力をありがとうシゲキさん。 めでたく記念撮影を終え、乱れた衣服を再び身につけたオレは、近隣住民にアンケートをとることにした。近隣といってもさっきから周りをうろちょろしている赤道軍団なのだが、どうしても聞いておくことがある。 「あのー、みなさんにちょっと聞きたいことがあるんですけど」 「なんだ?」 「ぶっちゃけ、今夏ですかね冬ですかね??」 「……。おまえアホか? 夏に決まってるだろう! こんな暑いんだから!!」 おおっと! 予想外に結構断定的な答えが返ってきた。オレとしてはどっちともない回答を期待していたのだが、どうやらまだこのあたりの地域は夏ということになっているらしい。しかしそれならば一体境目はどこなのだろうか?? とりあえず、オレはもう一歩踏み込んで聞いてみた。 「でもね、学校で習ったんですけど、北半球と南半球は季節が逆になるんですよ。だから、今まで通ってきたアフリカが夏だったから、赤道を越えてここからは冬になるんじゃないかと思うんですが」 「おー。そうか……」 「どうですか??」 「……。やっぱり今は冬だよ! 冬!」 「……」 どっちなんだよ!!! おまえら自分の町の季節にもっとポリシーを持てよ!!! 別にオレは毎回毎回赤道にコントをやりに来ているわけではない。しかし住人から返ってくる普通の反応がこれである。そら文字もでかくなるというものだ。まあいい、とりあえず今日のアンケートでわかったこと、それは赤道直下の町に住む人々には季節感が無いということである(涙)。 赤道をネタにして思いつくことはあらかたやりきったオレは、午後になりナニュキの町を出て、北へ向かった。次の町は、いよいよエチオピアへの玄関口、イシオロである。さあ、いよいよ文明が遠ざかっていくのを感じますよ。 このイシオロという町は、ケニアを走るバスの終点である。つまりどういうことかというと、ここから北は公共交通機関が全く存在しないのだ。ついでに言うと、時々ゲリラが出るらしい。 ここから先の地域は、以前「電波少年」でアフリカ大陸縦断ヒッチハイクにチャレンジしていた朋友ですら、危険地帯だということで移動方法が見つからず、苦渋の決断の元に禁断のワープをしている。 ただ、彼らがヒッチハイクに挑戦したのはもう5年以上前、作者がカラオケに行くと毎回細川ふみえの『にこにこにゃんにゃん』や『だっこしてチョ』を歌って踊っていた時期であり、今にいたるまでに多少情勢は変化している。 現在はイシオロから「ローリー」と呼ばれる大型のトラックがエチオピアとの国境の町まで走っており、そのトラックと交渉し、運転手にいくらか料金を支払うことにより荷台に乗せてもらうことができるのである。そしてトラックの荷台で2日がかりで国境まで向かうのだ。 ……え? そういうシステムができあがってるなら公共交通機関が全く存在しないなんて大袈裟に言うなって?? ……。 大袈裟に書いといた方がワイルドな旅に見えるだろうが!!! 「料金を払ってトラックに乗りました」より「トラックと交渉してなんとか国境まで乗せてもらえることになった」の方が凄いことに感じるだろうが!! イメージアップを狙ってるんだよ!!! さて、イシオロの町に到着した頃にはもう夕暮れ、アフリカの旅には珍しくシトシトと雨が降り出していた。とりあえず、明日(トラックの荷台で1日過ごす予定)は頼むから晴れてくれ(号泣)。 さびれた商店街で真っ赤なマサイマントを購入し、明日に備える。なにしろもうここは理論的には真冬だし、山岳地帯も迫っており気候の変化に対応する準備が必要だ。この町は非常に小規模で、都心部とは大分離れているため治安の心配はない。夜になりマサイマントを手に、その日の宿の周辺をウロウロしていると、小さな銀行の前に立っている警備員が駆け寄ってきた。 「おまえマサイマントを選ぶなんていいセンスしてるじゃないか!」 「センスをお褒めにあずかりありがとうございます」 「実はオレもマサイ族なんだ。出稼ぎでこんなとこで警備員やってるけど」 「へー。やっぱり戦士だけあって警備員が適職なんですね」 「ああ。ファイターだからどんな敵が来ても怖くないからな。でも明日の朝まで15時間もここに立ってなきゃいけないんだが、それが強盗と戦うより苦しいんだ。まったくマサイ族使いが粗いやつらだよ、ここの経営者は」 「たしかに遊牧民として一箇所にじっとしているのは辛そうだな……」 彼はケニア北部出身のマサイ族で、名前はホレレカヤというそうだ。ナイロビのカションバイといいホレレカヤといい、相変わらずとことん日本人離れしている名前である。彼は仮にも銀行で仕事をしているだけあって英語が話せ、せっかくの機会なのでいろいろと話し込んだ。特筆すべきは、彼は今24歳なのだが、5年前に成人の儀式でライオンと戦ったということである。 「ナロクという場所の近くにオレたちは住んでいるんだが・・・。成人を迎える7人で一組になってな、ライオンと戦うのがしきたりになってたんだ」 「まじで!! なんかアフリカの原住民みたい……」 「そのものだよ!!! グループで囲んでいくんだけど、そのうち追い込まれたライオンが飛び掛ってくるんだ。そしたらすかさず地面に槍を突き立てて、オレはグラインドして逃げる。そうするとライオンが槍に突き刺さるんだ」 ホレレカヤの話によると、やはり何人ものマサイがこの儀式に失敗して命を落としているらしい。戦士として成人を迎えるとは、こんなにも厳しいものなのか。しかしこの際、日本でも成人式で騒ぐ奴らにはライオンと戦うことを義務づけたらどうだろうか? 「いいか、おまえも将来のためによく覚えておけ。ライオンに噛まれそうになったら、ウィスカー(ひげ)を思いっきり掴んで睨みかえすんだ。おびえたり逃げたりしたらすぐやられるから、絶対怖がるんじゃないぞ!!」 「いや、将来その知識を実用する機会はないと思うのですが……」 「これって、トリビアになりませんかね?」 「ならないよっ!!! どうやって検証VTR作るんだよ!! そんな生活の知恵は日本人には必要ないぞ」 「じゃあ、これはどうだ? オレ達マサイの槍はとことん磨きあげて鋭利に造られているんだ。ゾウを狙って投げると、胴体を貫通して向こう側に突き抜けるくらいなんだぞ」 「なんかそれはゾウがかわいそうだ」 「でもオレたちは外国の奴らと違って必要以上に動物を殺すことはないんだ。ゾウもライオンも人間も同列に暮らしていて、マサイ族はおまえたちのように野生の動物を追いやって自分達の家を建てるなんて身勝手なことはしないぞ。あくまでも一緒に生きているんだから」 「へ〜へ〜へ〜すごいごもっともです」 「今度よかったらオレの村に招待してやるよ。次はいつ来るんだ?」 「次か……。多分、次は無いと思う……」 「そうか。残念だな。でももしかしたらまた来るかもしれないよな」 「そうだね。絶対ってことはないからね……。もし何年か経ってまたケニアに来ることがあったら、その時はきっと」 「よし! じゃあとりあえずまた明日の朝会おう!」 「うん、それまで仕事がんばってハレルヤン」 「ホレレカヤだっ!!!」 ケニアの片隅で、凄い勢いで出来ては消えて行く絆。たとえ親戚の子供は無視しても、こうして地球の裏側で出来上がった駆け出しの友人とすぐにさよならをしなければいけないことが、一度考え出すととことん深みにはまる謎である。この混乱を一旦経験してしまうと、ウルルン滞在記の別れのシーンを見ると毎回つい油断して心の汗を流しそうになってしまうのだ。 ハレルヤンとオレの人生が交わるのはきっとこれが最初で最後だろう。だがもし次の機会があれば、できればエアコンとホットシャワーと水洗トイレとインターネット環境を用意しておいてほしいが、ぜひ喜んでマサイの故郷へお宅訪問したい。たとえ子供が生まれた親戚の家への招待は断っても。 それにしても、自分の知らないところで知らない人の人生が動いているというのが、いつもいつも実に不思議なことである。 今日の一冊は、事実は小説より奇なりすぎる傑作 いま、女として―金賢姫全告白〈上〉 (文春文庫)  |
TOP NEXT