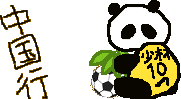 〜マサイの中心で、オカマと叫ぶ(後)〜 オカマ疑惑が払拭された頃にはいつの間にか昼近くになっており、遂にマサイ村を訪れる時がやって来た。もちろん訪れるといっても、光通信でもあるまいしアポなしでいきなり訪問するのではない。おそらくそんなことをしても居留守を使われるか、「うちはテレビがないから受信料なんて払わないモジャリ!!」とインターホンごしにスワヒリ語でバレバレのウソをつかれるに決まっている。 ということで多少拍子抜けされるかもしれないが、今から訪問するところは事前に派遣のテレホンアポインターさん(時給1300円)を使ってアポ済み、ではなく旅行会社と契約して受け入れ態勢が整っているマサイ村なのである。ただ、だからといって特別なところではなく、サバンナに点在し実際にマサイ族が暮らしている、れっきとした本物マサイ村である。同じ観光用の村でも、営業時間が終わると住人である忍者がマイカーで帰宅する日光にある村とはリアルさが違う。 ここでまずマサイ族の村という概念について説明せねばなるまい。彼らの場合、村というよりも集落で、それぞれの集落は周囲を木の枝や高い藪で囲まれ、完全に独立している。そしてその独立した集落の中には、多くてもせいぜい200人くらいしか住んでいない。「今日は部長と接待ゴルフなんだよなー」と奥さんにボヤいて出かけ、こっそり愛人とデートをしても、一瞬で村民全員に行動が筒抜けになる規模である。 まあその場合は集落を出て遠くまで逢い引きの場所を広げればいいのだが、一歩村から出てしまうと不良はいなくともゾウとかヒョウとかにからまれる可能性がある。さらに川などに入って、「アハハハ! それ! それ!」「キャッ! つめた〜い! もう、やったな! えいっ!!」「ブワッ! ごめん! わるかったよ!!」「許さないんだから! もう、カションバイのバカ! えい! えい!」などとじゃれあっているうちにワニに喰われるだろう。普通男は体を張って彼女を守るものだが、ワニやライオンの群れにからまれた日にはそれこそ本当に体を捧げて彼女を逃がさなければならない。そのシーンを「自分を犠牲にして彼女を守った美しい話」として映画化しても、恋愛映画というよりスプラッタ映画になりそうである。 さて、下の写真がマサイ村の入り口であるわけだが、このように木の枝などで壁を作り、人の出入りする時だけ門を開ける。サバンナの真っ只中にあるために、こうでもして隔離しないと強制的に村の中に動物王国ができあがってしまうのだ。日本の農村地区のニュースで時々、「クマが山から下りて来て民家に侵入」というようなものがあるが、ここの場合はあらゆる肉食獣が村を食い尽くすことが考えられる。  村の正面で車を止め、じゃあそろそろお邪魔しようかな……と村に入ろうとすると、なんと他の客も、そしてドライバーすらオレについてこない。 「ねえ、みなさん、早く行きましょうよ。村を訪れに。そして子供達とふれあい、地域交流を深めましょう」 「いや、実はオレ達はもう昨日一度来たんだ。だからここでおまえを待ってるから、一人で楽しんで来い」 「ガビーン!!!」 なんですと!! 一人ですと!!! いや、せめてガイドくらい一緒について来てくれないか? 外で待ってるってそれガイドになってないんじゃ…… 「ヘイ! ユー! ハバリムズリジョモンガ!! カモーン」 ところどころ片言の英語が混ざった呼びかけの声に目をやると、藪に囲まれた集落の中から、2,3人の真っ赤な装束のマサイ族が槍を持ってオレを手招きしている。 「ちょ、ちょっと待って。なんか一人で入るのは怖い……」 「ナホ!! タムジャリナマンガ!!!」 「は、はいっ!! すいません。だ、大至急お邪魔させていただきます」 マサイ語でもなぜか雰囲気で意味がわかってしまうことにやや驚きをおぼえつつ、東洋人代表として一人で村へ入っていく。イバラの門をくぐった途端、集落内にいるマサイ族の目が一斉にオレに注がれる。た、たのむ、たしかにオレは黄色人種だが、黄色いからといってライオンと間違えて狩るのだけはやめてくれ。 集落の中は周囲を完全に藪に囲まれているため想像以上に狭く感じる。中央には何も無い広場があり、その広場を囲うように円形に家が建っている。 「よく来たな! さあ、こっちだ」 「ど、どうもモジャ」 「おちょくってんのか!!!」 「ひいいっ! すいません!!」 「ここはほんの50人しか住んでいない集落だが、大きな村と全く変わらない造りになってるんだ。この中は写真撮り放題だぞ」 「すみませんなんか気を使っていただいて……」 「いえいえ」 オレを呼び入れてくれたこのマサイ族の青年は、普段も村の案内役をしているらしく、大体オレと同レベルの、イクラちゃんクラスのカタコトで英語が話せるようだ。ちなみに本人同士は真面目に話しているつもりだが、オレ達の会話をネイティブが聞いたらバブバブ言っているようにしか聞こえないだろう。 「よし!! 男ども全員集合!!」 「は、はい!」 「おまえはいいんだ」 「あら? そうですか?」 案内マサイがひと声かけると、集落の中の戦士のマサイが全員集まってきた。マサイ族の男は、毎日朝早くからたくさんの牛を連れて放牧に出かけ、一人で何十頭もの牛を管理する。牛を扱わせたらパペットマペットといい勝負をしそうなくらいのプロフェッショナルだ。そんな彼らの大仕事といえば、牛をライオンなどの肉食獣から守り、戦うことである。よってマサイ族の戦士といえば、この場合若い男全員をさす。 「じゃあわが友人の来村を祝って、本日のマサイダンスだ!!」 「へーイ!」 マサイ達は、1列に隊列を組むと軽く掛け声をかけてスキップを始めた。広場をジグザグに進みながら、一人ずつ順番になにやら呪文のような、歌のような文句を唱え、ところどころで全員で斉唱する。こ、これは、我が中京大学少林寺拳法部のランニングと全く同じではないか!! ということは、へばって声が出なかったら幹部(4年生のこと=神)から容赦なく「やり直せ!!」と怒鳴られたり、集団から遅れたら「作者あ〜!! おくれてんじゃね〜よ!!!」と統制部長からしばかれたりするのだろうか。 ……。 なんか思い出したら動悸が激しくなってきた(涙)。お、おちつけ。今はもうオレは社会人なんだ。部活はもう卒業したんだ……。はあ、はあ……。 しかしよく見ると、マサイ達は妙にちんたらやっているような気がする。おそらくいつもは客はグループで来ているだろうから、オレひとりだけが相手ではたしかにやる気も半減するだろう。 「よ〜し、ニメチョカ〜!」 掛け声と共に今度はわらわらとオレのまん前に集まり、戦士達はひとりずつ交代で前に出てビヨンビヨン跳ね出した。なるほど。これが噂のマサイジャンプね。……しかしマサイジャンプという名称がついているわりには、それこそただ跳ねているだけである。たしかにスポーツテストの垂直跳び学年ベスト30に入り廊下に貼り出されるくらいの跳躍力はありそうだが、別にスーパーマリオや麻原(ピー)晃のように自分の背丈の5倍も6倍も高く飛んでいってるわけでもない。オレもスポーツテストでは測定するための黒板を必要以上に低く設定しておくのが得意だったので、記録上はマサイといい勝負が出来そうである。オレも帰国後は「マサイから教わった作者ジャンプを見せてやるぜ!」と友人や親戚から金を取り、ぴょんぴょん跳ねて見せてやるとしよう。 「女ども! 集合!!」 「は〜い!」 次はカラフルな格好をしたマサイの女性がオレの前に横一列に整列し、歓迎の歌を歌い出した。……マライアやセリーヌも真っ青な高らかな歌声である。しかし、中の2,3人の若い子が視線が定まっておらず、明らかに照れているのが気になる。そして、一人で歌を聴くはめになっているオレもかなり恥ずかしい。こういう時はどういう態度をとっていればいいのか。『愛は地球を救う』でゲストの歌を聞く局アナのように、リズムに合わせてにこやかに首を左右に傾ければいいのか? それともものまね王座決定戦の審査員のように、ヘッドホンを逆向きにして両手で押さえながら、びっくりした顔をして聴けばいいのか?? 結局オレは、心の中で20通りくらいのリアクション方法を考えながら、最後まで仏頂面で歌を聴いていた。自分のキャラクター以上のことは、できません。 「ららら〜……♪」 歌が終わった。 パチパチパチ……。一応国際的な礼儀として、がんばって笑顔を作り感謝を込めた拍手をしておく。 ……。 気まずい。 歌い終わったマサイ族も彼女達なりにこの拍手が国際的な義理だということをよくわかっており、「この空気をどうしましょう……」という困惑を硬直した笑顔でおもいっきり表している。そして一人の客の前で解散するきっかけを掴めずにいる。多分白人のグループだったらもっと情熱的な拍手と「ブラボー!」とか声援が飛ぶんだろうが、悲しいことにオレの脳はそういうことをするようにプログラムされていない。 ……。 ……(お互いそのままの体勢で固まること2,3分)。 「さーじゃあ次は村の中を案内してやろう! よし、みんなは帰った帰った!!」 幸いにも案内役のマサイの仕切りで、女性達はバラバラと村の四方に散って行った。た、助かった。
「ジャパニーズ! この槍を見てみろ。おれ達はこれでライオンとかゾウも倒すことができるんだ」 「うわ……。す、すげ……この槍が日本にあれば、B29だって叩き落すことが出来たのに……」 「それは無理だが、マサイには倒せないものなんてないんだぜ!」 「戦士だね。ついでにナイロビの強盗もお願いしたいんだけど」 「いいか、よく見てろよ。槍を投げる時は、少し下の方を持って、こうやってよく狙いを定めて……」 「パージェーロ! パージェーロ!」 「なんだそりゃ??」 「いや、日本では鋭利な武器を投げる時にはこの掛け声が基本でして」 「そうか。まあとりあえず我が家に招待しようじゃないか。さあ、こっちだ」 2人のマサイについて、一軒の家へ案内される。ちなみに、マサイ族の家は一般に藁と牛フンでできている。骨組みこそ土や木だろうとは思うが、牛フンを塗りこみ、カチカチに固めている。なんかもうこの場では普通に感じてしまうが、冷静に考えてみればそれはもの凄いことではないのだろうか? 尚、多分耐震設計はされていないだろうが、逆にマサイ家屋は地震で全壊してもフンにまみれるだけで済みそうだ。むしろ地震大国日本ではこういうフン設計を少し取り入れた方がいいのではないだろうか。おもらしした時も壁に塗り込んでごまかせるので、もしもの時の対処も楽だ。 「よく来たな」 「はい。おじゃまします……って何も見えねー!!」 牛フンで塗り固められたマサイ家お宅訪問だが、そもそも電気などというエジソン的なものはここにはない。そして、藁で出来た家のため火も使えない。よって、招待されたはいいが家の中は漆黒の闇である。 「あの、すいません!! マサイさん、どこにいますか??」 「ここだよ」 「どこ?」 「こっちこっち」 「……」 うーむ。家主は100%闇に同化しており、その居場所をつきとめるにはFBI超能力捜査官にでも透視してもらう必要がありそうだ。オレは少し透視にチャレンジしてみたができなかったので、携帯用のミニ懐中電灯を出して枝とフンの小屋へ文明を持ち込んだ。 「うおっ!!! そ、そこにいらっしゃいましたか……」 「ほほー。おまえ便利なもの持ってるな。ちょっとこっちを照らしてくれよ」 闇の中にボーっと浮かび上がった、武器を持つマサイ族の姿。こんなもん日本のオレのアパートで見た日には絶対チビるだろうが、ここがケニアのマサイ村であるためにかろうじて「そういうもんだ」と自分に納得させられる。これが適応というものだ。 小屋の中はジンバブエで訪れた予言者の村の家の構造とそっくりであった。木の枝で組んだベッドやテーブルがあり、生活感を感じさせる。 「さて、実はおまえにちょっと頼みがあるんだが……」 「な、なんですか? インターネットがうまく繋がらないとかですか?」 「どこから電源とるんだよ!! そんなことじゃないよ。ここに観光客からもらった20ドルばかしあるんだが、オレ達ケニア人だからケニアシリングに両替してくれないか?」 「あ、ああ、そんなことですか。いいですよ……」 オレ達は狭い小屋の中、懐中電灯で暗闇を照らしながら、こそこそと両替をした。葉巻をくゆらせながらゆっくりと紙幣を数え、後ろで待機する若いもんに顎で合図すると、スーツケースを机の上に広げブツを相手に確認させる。日本だったら舘ひろしと渡哲也が踏み込んで来てもおかしくない場面だ。 「よし、サンキューな」 「どういたしまして」 「じゃあそろそろお引取り願おうか」 「両替したかっただけかよ!!!!」 ということで、はやばやと用済みということでマサイ家から放り出されたオレは、集落の中をひと通り回ってみることにした。それにしても皆が皆、派手な格好である。戦士は全員が真っ赤な民族衣装を着ており、女性は逆にそれぞれ違う色のカラフルな着物を着ている。 彼らマサイの戦士は、敵から逃げることを最も恥とするという。たとえ相手がライオンでも人間でも、逃げるくらいなら死んだ方がマシなのだそうだ。まさしく生まれながらの戦闘民族である。ちなみにオレは、死ぬくらいなら逃げる方がマシという考えである。 ガサガサっ!!! 「キャーッ!!」 その時、数人の女性、子供マサイが集まっている脇の藪が突然ガサガサと動いた。そして、彼女たちが警戒する間もなく、なんと茂みから肉食獣が飛び出してくるではないか!! うわーーーっ!!!  マサイの村で暮らしている犬でした。 ……。 なんで犬がこんなとこにいるんだよ!! あれだけアフリカのサバンナを走り回って一匹もいなかったのに!! ここアフリカでも、マサイ族の世界ですら、もう犬は完全に人間側の存在らしい。本来は動物として弱肉強食の世界で生きていかなければならないはずなのに、野生から姿を消したと思ったらうまく人間社会の方で生きている。なんて利口なやつらなんだ……。 最後にみんなで記念撮影をし、案内役を買ってくれたマサイと握手を交わし村を後にする。ナイロビに帰る途中、同じようなマサイの集落をいくつも窓の外に見る。我も人なり、彼も人なりであるが、その距離感はいかんとも表現しがたい。しかし一見資本主義社会とはなんの関わりもなさそうに見える彼らマサイ族も、この時東洋の国日本では大手製薬会社から「マサイ族も飲んでいる! 乳飲料マサイの戦士」としてその名を冠した商品が発売され、宣伝のために日本に呼ばれた同胞のマサイの戦士が固いコンクリートの上でマサイジャンプをして膝を痛めていたとは、決して知る由もなかっただろう。 今日の一冊は、……私は薩長よりも新選組派です 燃えよ剣〈上〉 (新潮文庫)  |
TOP NEXT

