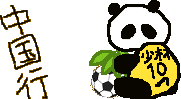 〜ラリベラ−ガシュナ〜 アフリカだけでなく途上国を旅していると、食事時ですら適わぬ恋に悩んでいる女子中学生くらいの勢いでひたすら悩むということが幾度もある。ちなみに女子学生というものはなぜか必ず先輩(運動部所属)との恋に悩むように出来ているので、男子生徒の場合は彼女を作ろうと思ったらたいてい自分が上級生になるまで待たなければならない(場合により転部も必要)。 とはいえ、モテる奴は1年生でもいきなり上級生の女子と付き合っていたりするので、結局美男子に生まれればそれでもう人生はバラ色ってことかよ。そうかよ。生まれながらにして幸せな人生が約束されてるのかよ!!!! ああいいねえ、いいとこの坊ちゃんはよ!!! 夜道は物騒だから気をつけて歩くんだな!!! ということで上記のように食事の話であるが、例えば、ケニア北部イシオロの町の安食堂でオレはシチューを頼んだのだが、「おまたせ〜」とテーブルに皿が置かれたその瞬間、あつあつのシチューに2匹のハエが何の躊躇もなしに捨て身のダイブを敢行した。当然彼らは全身火傷で即死していた。 ……あんたら、どれだけ腹減ってたんだ?? いくら飢えてたとはいえ、巨大なシチューの海に全身でつかるとは、あんたらはハエの世界のビートたけしと明石家さんまか(byおれたちひょうきん族)?? とりあえず命よりも食事優先かよ……。まあハエにはハエの生き様があるだろうし、死ぬほど腹へって本当に死んでいるというのは有限実行で立派と褒められるべきものかもしれないが、ただ後に残されて困るのはそのシチューをこれからすすらなければならないオレである。 とりあえず、オレはハエの溺死体から最も遠い場所から、猛スピードでシチューを飲み始めた。オレの脳内イメージでは、今頃ハエの死体からはいい具合にダシが出て来ているはずなのだ。表面上は見えないが、2匹の死体を中心に波紋のようにジワジワと広がっているダシ、蝿のエキスが到達していない範囲、そこだけが食べていい場所なのである。ハエエキスに侵食される前に、少しでも多くのシチューを救う。それがオレの役目。オレとエキスのデッドヒートだ。 ちなみに上の文章にはシチューを「救う」と「掬う」がかかっているという、ちょっとした言葉遊びの要素が入っています。ユニークでしょう。 しかし、あくまでハエのダシは目に見えるものではないので、結局オレはどこまでが蝿という列強に犯されず独立を保っている地域か判断ができずに、大事をとって半分以上のシチューを残さねばならなくなった。ハエが半額払っているならば納得もできよう、しかしこのシチューに料金を支払っているのはオレだけなのだ。それなのにハエと折半しなければならないというのはあまりにも合点がいかなかった。しかも知り合いではなく赤の他蝿である。 そしてここラリベラで出てきたワット(ビーフシチュー)は、今度はハエではなくのちに毛だらけワットと命名したほど、ギネスブックに申請しようと思ったくらい、記録的に毛だらけなものだった。 この場合の毛とは髪の毛のような長いものではなく、まつ毛であった。ただ、本当に人間のまつ毛であるかどうかはわからない。何しろ、ワットをスプーンで掬うと必ずひと掬いに2本はそのまつ毛が入っているのだ。これだけの量となると、たまたまということではなく、何か肉についていた動物の毛でも入ったものなのか、それともあえて店員のまつ毛を食材に使用しているのか、いずれにしても食えるかバカヤロー!!!!!!! オレは猫じゃねーんだよ!!!! 毛玉だけ後から吐けるような丁寧な体質じゃないんだよっ!!! それでもオレはまだこのワットを食べ物として復活させてやろうと、周りのシチューと一緒に毛を丁寧に拾い、従業員の見ていないところで後ろの茂みに掬っては捨て、掬っては捨てていった。ちなみにここは食堂であるが庭にテーブルが並べられているだけで、ノラ犬も足元をウロウロしている。 まあ普通の感覚ではこういう場合は店員を呼ぶわけだが、途上国ではその感覚は通用しない。日本とは違うので、どうせハエや毛が入っているからといって謝りも取替えもしないし、「王様のブランチ見たんですけど」と言っても割引が適用されることもない。 結局ワットの中から全ての毛を捨てていったら、3分の2くらいのシチューを捨てるハメになり、さすがにもうそこから食う気は起こらなかった。一口も飲まずに店を出たわけだが、量としてはだいぶ減っているので店員も客が料理をたくさん残したと傷つくことはないだろうし、捨てたワットは捨てる端から全てノラ犬が食べているので、証拠も残っていない。これで一件落着である。オレはこのレストランで、金を払って、シチューから毛を一生懸命取り除いて、自分はメシも食わずに帰るというおもしろい経験ができたわけだ。ふざけんなコラっ!!!!!! 途上国でメシをおいしく食べるためのコツは、もしかしたら目隠しをしながら食べるということなのかもしれない。見えさえしなければ、きっと汚いからと気になることはなく、ハエの死体もおいしく食えば、まつ毛も飲み干すだろう。書いてて吐きそうになってきた。 尚、ラリベラも他の町と同様電気はほとんど来ていない。そのため夜は外にいると視界が完全にふさがれ現在地を見失い、海の男でもないのに北極星の方向を頼りに宿まで帰らねばならないのである。ただ航海中と違い、ラリベラの場合は方向だけ合っていても油断をすると途中で崖下に転落したりするので、さらなる注意と運が必要になってくる。 いちおうここには教会が豊富にあり、事故死しても葬式に呼ぶ僧侶に困ることはないだろうが、まだまだオレにはやることがいっぱいあるのだ。真・三国無双にファイアーエムブレムにドラクエの新作ね。あと未知なる優良なアダルトサイトの発掘とか、いろいろあるわけさ。それに多分こんな場所では日本から最短で4日くらいかかるので、知り合いも誰も弔問に来てくれないだろうし。 宿では部屋にロウソクを置いて過ごし、やはりトイレなどは懐中電灯をくわえて行かざるおえない。しかしおもしろいのは、たまに電気がつくとどこかからか村民の「ワ〜ッ!」という歓声が聞こえてくるのだ。電気がつくかどうかというのが村をあげての関心事となっている。昨今つくかつかないかでこれだけ盛り上がるというのは、エチオピアの電気か万景峰号くらいであろう。 教会の見学をした次の日、たった2泊の滞在でオレはラリベラを後にし、次なる町バハルダールへ向かうことにした。やはり朝5時半発のバスで。暗闇を懐中電灯で照らしながらバス停まで歩くわけだが、なぜかラリベラのバス停には旅行者を見ると叫びながら石を投げてくるばあさんがいるのである。あれ? 人がいるなあ、と思って前方を照らしたら突然鬼気迫る表情のばあさんが浮かび上がり、絶叫とともに攻撃をしかけてきた日には、オレは泡を吹いて気を失う寸前であった。 9時前に、乗り換えポイントであるガシュナという場所へ着いた。ラリベラから直通のバスが無いため、うっとうしいことにここでアジスから来るバハルダール行きのバスが通るのを待たなければならないのだ。1日1本しかない、通過時間未定のバスを。 一応ここはガシュナと名前がついているだけあって村であるわけだが、近くにチャイ屋が一軒あるだけで、他はもう村というより、もしここに人の姿がなかったら、学者が「おおっ! こんなところに20万年前の集落跡が!!」と断定し学会で発表しそうなくらいさびれており、日本昔話に出てくる村が政令指定都市に見えるくらいの異次元の世界であった。 道端でおばさんがノラロバをビンタする摩訶不思議な光景などを見ながら集中してバスらしき物影が現れるのを待っているのだが、それにしてもここは異様に蝿が多い。ただ突っ立っているだけで、常時5匹から10匹の蝿が体のどこかに止まろうとしているのである。 本来この地球は人間だけのものではなく、その他の生き物、小さな命たちと共生していかなければならないものだが、1時間、2時間と顔の周りを蝿に飛び回られるにつれ、人生で3回しか怒らないことにしているこのオレも、いい加減堪忍袋の緒が切れた。ちなみに時々カラオケでいとしのエリーの「エリー♪ マイラーブ♪」のところを、エリーを自分の彼女の名前に変えて歌う奴がいるが、それを見た時もオレは人生で3回しか怒らないうちの1回を使って激怒する。 さて、オレはバックパックから生物兵器であるキンチョールを取り出し、飛ぶ蝿止まる蝿全てに向かってかけまくった。殺す殺す。とことん殺す。全盛期のルー大柴とは違いただうざいだけではなく、伝染病などの病原菌の媒体ともなる人類の敵であるのだ。オレの周りの蝿だけでなく、おもしろがって周りにいた村の住人までもが自分の手や足に止まっている蝿を「これも殺してくれ」と頼んでくるもんだから、オレは人体への影響など全く考えずに彼らの体に向かって噴射しまくった。おそらく彼らも村を苦しめる蝿軍団にはうんざりしていたのだろう、ポタポタと蝿が落ちていくのを見て、ヤンヤヤンヤの大騒ぎ。ある意味オレは村の救世主である。きっと村の教会にある聖典には、何千年も前からこの日の救世主降臨のことが予言されていたことだろう。 10匹、20匹では済まず、おそらく奪った命は3桁に突入したに違いない。普段ならこんなことはしないオレなのだが、今日の私、ちょっと大胆。 ということで、虫も殺せぬ性格のオレは引き続きうんざりしながらバスを待っていたわけだが、それにしても本当に今日ここに該当するバスは来るのだろうか。周りの奴に聞くと来る来るとは言うが、もう昼は12時である。すでに3時間もボーっと待っているのだ。まさかオレがここに到着する前にもう通り過ぎてしまったんじゃないだろうか。来る来る言われておいて実際には来なくても喜ばれるのはなつかしの恐怖の大王くらいで、バハルダール行きのバスの場合は大王とは違い来なかったら悲しい。いやもとい、バハルダールへ行くには例によって2日かかるので、正確にはバハルダール行きのバスではなくバハルダールへ行く途中の村行きのバスである。勘弁してくれ。 おっと。とかなんとか言っているうちになんかバスが1台通り過ぎて行ったぞ。あれはなんだ? ……。 「ちょっと、そこのエチオピア人のにいさん」 「なんだい?」 「今我々の前を通過して行ったバスはどこ行きですかね??」 「ああ、あれがバハルダール方面行きのバスだよ」 「そうですか。どうもありがとう」 ……。 「待てっ!!!! 乗せてくれっ!!!! 置いてくんじゃねー!!!!!」 「ん? おまえあのバスに乗るのか?」 「そう、そうです!! バハルダール方面に行きたい人です私は!!!!」 「よっしゃ、オレにまかせろ!!!」 ここに一旦止まるという噂だったのに、なぜか明らかに乗客である20キロのバックパックを背負った外国人を無視して、バスは演歌をかき鳴らしながらノソノソと前方を走って行く。くそ、この鬼畜ドライバーめ!!! しかしオレはラッキーだった。この時たまたま話しかけた若者が、なんと全速力でバスを追いかけ、停車させてくれたのである。 「お〜い、日本人! 席あるってさ。はやく乗れよ」 「おおっ!!! す、すみません! てめー鬼畜ドライバー!! オレがケンカに拳を使えない立場で助かったな!! もしオレがプロボクサーじゃなかったら今日がおまえの命日だ!!」 救世主をあがめる村民の親切なエチオピア青年のおかげで、なんとか非人道的なエチオピア年配の運転する1日1本という、ニホンカワウソなみに個体数の少ないバスを掴まえることができた。絶滅が危惧されているのでこのように捕獲には非常な努力を要する。 こうしてオレは再び演歌を聴きながらバハルダールへの途中の村へ向かってまたバスの中で1日を費やす。 今日の一冊は、死ぬまで仕事に困らないために20代で出逢っておきたい100の言葉  |
TOP NEXT